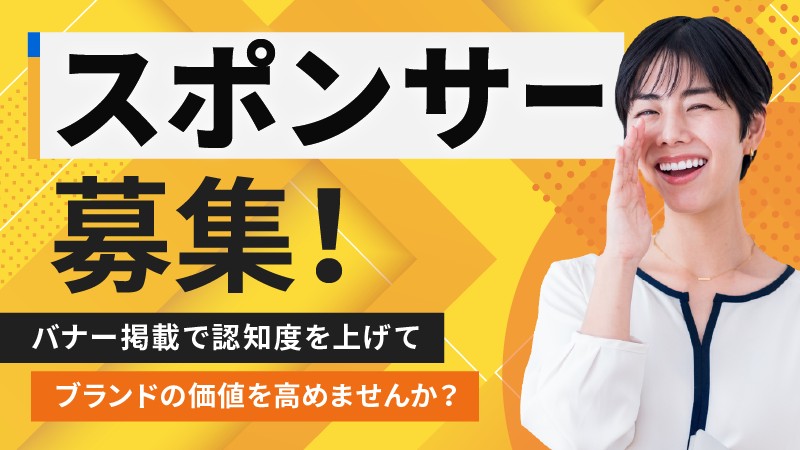行列の性質
行列の性質
加法は\(\forall A,B\in M_{m\times n}\left(K\right),A+B\in M_{m\times n}\left(K\right)\)である。
\(K\)上のスカラー倍は\(\forall\alpha\in K,\forall A\in M_{m\times n}\left(K\right),aA\in M_{m\times n}\left(K\right)\)である。
また、\(A,B\)が共に同じサイズの正方行列のときでも一般的に\(AB=BA\)は成り立たない。
\(m\times n\)行列\(A\)に右から単位行列\(I_{n}\)を掛けると、\(AI_{n}=A\)となる。
\(n\)次正方行列\(A\)に単位行列\(I_{n}\)を右から掛けても左からかけても\(I_{n}A=AI_{n}=A\)となる。
\(m\times n\)行列\(A\)に左から\(O_{l,m}\)を掛けると、\(O_{l,m}A=O_{l,n}\)となる。
\(m\times n\)行列\(A\)に右から\(O_{n,l}\)を掛けると、\(AO_{n,l}=O_{m,l}\)となる。
\(n\)次正方行列\(A\)に\(O_{n}\)を右から掛けても左からかけても\(O_{n}A=AO_{n}=O_{n}\)となる。
零行列でない\(A\ne O\)があるとき、\(\exists B\ne O,AB=O\lor BA=O\)を満たすとき、\(A\)を零因子という。
このときの\(B\ne O\)は\(A\ne O\)であり、\(AB=O\lor BA=O\)をみたすので\(B\)も零因子となる。
\(A=B\)のときはべき零行列になります。
(1)ベクトル空間
体\(K\)(複素数\(\mathbb{C}\)または実数\(\mathbb{R}\))を成分とする\(m\times n\)行列\(M_{m\times n}\left(K\right)\)は次の加法と\(K\)上のスカラー倍に関してベクトル空間になる。加法は\(\forall A,B\in M_{m\times n}\left(K\right),A+B\in M_{m\times n}\left(K\right)\)である。
\(K\)上のスカラー倍は\(\forall\alpha\in K,\forall A\in M_{m\times n}\left(K\right),aA\in M_{m\times n}\left(K\right)\)である。
(2)非可換
\(AB,BA\)が同じサイズになるのは\(A,B\)が共に同じサイズの正方行列のときのみである。また、\(A,B\)が共に同じサイズの正方行列のときでも一般的に\(AB=BA\)は成り立たない。
(3)単位行列
\(m\times n\)行列\(A\)に左から単位行列\(I_{m}\)を掛けると、\(I_{m}A=A\)となる。\(m\times n\)行列\(A\)に右から単位行列\(I_{n}\)を掛けると、\(AI_{n}=A\)となる。
\(n\)次正方行列\(A\)に単位行列\(I_{n}\)を右から掛けても左からかけても\(I_{n}A=AI_{n}=A\)となる。
(4)零行列
\(m\times n\)行列\(A\)に\(O_{m,n}\)を足すと、\(A+O_{m,n}=O_{m,n}+A=A\)となる。\(m\times n\)行列\(A\)に左から\(O_{l,m}\)を掛けると、\(O_{l,m}A=O_{l,n}\)となる。
\(m\times n\)行列\(A\)に右から\(O_{n,l}\)を掛けると、\(AO_{n,l}=O_{m,l}\)となる。
\(n\)次正方行列\(A\)に\(O_{n}\)を右から掛けても左からかけても\(O_{n}A=AO_{n}=O_{n}\)となる。
(5)零因子
行列は\(AB=O\)であっても\(A=O\lor B=O\)とは限らない。零行列でない\(A\ne O\)があるとき、\(\exists B\ne O,AB=O\lor BA=O\)を満たすとき、\(A\)を零因子という。
このときの\(B\ne O\)は\(A\ne O\)であり、\(AB=O\lor BA=O\)をみたすので\(B\)も零因子となる。
\(A=B\)のときはべき零行列になります。
(6)可換とスカラー行列
\(n\)次正方行列\(A\)があるとき、任意の\(n\)次正方行列と可換であることと、\(A\)がスカラー行列であることは同値である。(7)積の結合律
行列\(A,B,C\)があり、積に関して結合律、すなわち\(\left(AB\right)C=A\left(BC\right)\)が成り立つ。(8)分配律
行列\(A,B,C\)があるとき、積の和に関する左分配律と右分配律、すなわち左分配律\(A\left(B+C\right)=AB+AC\)、右分配律\(\left(A+B\right)C=AC+BC\)が成り立つ。(1)
\(A,B,C\in K^{m\times n};a,b\in K\)とする。(a)加法の結合律
任意の\(\left(i,j\right)\)成分について、\begin{align*} \left(A+\left(B+C\right)\right)_{i,j} & =\left(A\right)_{i,j}+\left(B+C\right)_{i,j}\\ & =\left(A\right)_{i,j}+\left(B\right)_{i,j}+\left(C\right)_{i,j}\\ & =\left(A+B\right)_{i,j}+\left(C\right)_{i,j}\\ & =\left(\left(A+B\right)+C\right)_{i,j} \end{align*} となるので、
\[ A+\left(B+C\right)=\left(A+B\right)+C \] が成り立つ。
(b)加法の可換律
任意の\(\left(i,j\right)\)成分について、\begin{align*} \left(A+B\right)_{i,j} & =\left(A\right)_{i,j}+\left(B\right)_{i,j}\\ & =\left(B\right)_{i,j}+\left(A\right)_{i,j}\\ & =\left(B+A\right)_{i,j} \end{align*} となるので、
\[ A+B=B+A \] が成り立つ。
(c)加法単位元
\(m\times n\)行列の零行列\(O\)は任意の\(A\in M_{m\times n}\left(K\right)\)に対し、\(A+O+A\)となるので加法単位元が存在する。(d)加法逆元
任意の\(A\in M_{m\times n}\left(K\right)\)に対し、\(-A\)は\(A+\left(-A\right)=A-A=O\)となるので、加法逆元が存在する。(e)スカラー分配律
任意の\(\left(i,j\right)\)成分について、\begin{align*} \left(a\left(A+B\right)\right)_{i,j} & =a\left(\left(A\right)_{i,j}+\left(B\right)_{i,j}\right)\\ & =a\left(A\right)_{i,j}+a\left(B\right)_{i,j} \end{align*} となるので、
\[ a\left(A+B\right)=aA+aB \] が成り立つ。
(f)ベクトル分配律
任意の\(\left(i,j\right)\)成分について、\begin{align*} \left(\left(a+b\right)A\right)_{i,j} & =\left(a+b\right)\left(A\right)_{i,j}\\ & =a\left(A\right)_{i,j}+b\left(A\right)_{i,j} \end{align*} となるので、
\[ \left(a+b\right)A=aA+bA \] が成り立つ。
(g)スカラーとベクトルの結合律
任意の\(\left(i,j\right)\)成分について、\begin{align*} \left(a\left(bA\right)\right)_{i,j} & =a\left(b\left(A\right)_{i,j}\right)\\ & =ab\left(A\right)_{i,j}\\ & =\left(ab\right)\left(A\right)_{i,j} \end{align*} となるので、
\[ a\left(bA\right)=\left(ab\right)A \] が成り立つ。
(h)スカラー単位元
任意の\(\left(i,j\right)\)成分について、\begin{align*} \left(1A\right)_{i,j} & =1\left(A\right)_{i,j}\\ & =\left(A\right)_{i,j} \end{align*} となるので、
\[ 1A=A \] が成り立つ。
これらより、ベクトル空間であるための条件を満たすので、加法とスカラー倍に関して\(M_{m\times n}\left(K\right)\)はベクトル空間になる。
(2)
積\(AB\)が計算出来るのでは\(A\)が\(l\times m\)行列で\(B\)が\(m\times n\)行列のときで\(AB\)は\(l\times n\)行列となる。同様に積\(BA\)が計算出来るのでは\(B\)が\(p\times q\)行列で\(A\)が\(q\times r\)行列のときで\(BA\)は\(p\times r\)行列となる。
行列\(A\)については\(l=q\land m=r\)で行列\(B\)については\(m=p\land n=q\)であり、\(AB,BA\)が同じサイズになるのは、\(l=p\land n=r\)のときである。
これより、\(m=r=n=q=l=p\)となるので、\(A\)は\(l\times m\rightarrow l\times l\)行列、\(B\)は\(m\times n\rightarrow l\times l\)行列、\(AB\)は\(l\times n\rightarrow l\times l\)行列、\(BA\)は\(p\times r\rightarrow l\times l\)行列となる。
従って、\(AB,BA\)が同じサイズになるのは\(A,B\)が共に同じサイズの正方行列のときのみである。
一般的に\(AB=BA\)は成り立たない
一般的に\(AB=BA\)は成り立たないことの証明反例で示す。
\[ A=\left(\begin{array}{cc} 1 & 0\\ 0 & 0 \end{array}\right) \] \[ B=\left(\begin{array}{cc} 0 & 1\\ 0 & 0 \end{array}\right) \] とすると、
\begin{align*} AB & =\left(\begin{array}{cc} 1 & 0\\ 0 & 0 \end{array}\right)\left(\begin{array}{cc} 0 & 1\\ 0 & 0 \end{array}\right)\\ & =\left(\begin{array}{cc} 0 & 1\\ 0 & 0 \end{array}\right) \end{align*} \begin{align*} AB & =\left(\begin{array}{cc} 0 & 1\\ 0 & 0 \end{array}\right)\left(\begin{array}{cc} 1 & 0\\ 0 & 0 \end{array}\right)\\ & =\left(\begin{array}{cc} 0 & 0\\ 0 & 0 \end{array}\right) \end{align*} となるので\(AB\ne BA\)である。
従って、一般的に\(AB=BA\)は成り立たない。
(3)
\(A\)は\(m\times n\)行列なので、任意の\(\left(i,j\right)\)成分について、\begin{align*} \left(I_{m}A\right)_{i,j} & =\sum_{k=1}^{m}\delta_{i,k}\left(A\right)_{k,j}\\ & =\left(A\right)_{i,j} \end{align*} となるので
\[ I_{m}A=A \] となる。
同様に、任意の\(\left(i,j\right)\)成分について、
\begin{align*} \left(AI_{n}\right)_{i,j} & =\sum_{k=1}^{m}\left(A\right)_{i,k}\delta_{k,j}\\ & =\left(A\right)_{i,j} \end{align*} となるので
\[ AI_{n}=A \] となる。
\(n\)次正方行列\(A\)に単位行列\(I_{n}\)を右から掛けても左からかけても\(I_{n}A=AI_{n}=A\)となる。
-
\(A\)を\(n\)次正方行列とすると、任意の\(\left(i,j\right)\)成分について、
\begin{align*} \left(I_{n}A\right)_{i,j} & =\sum_{k=1}^{n}\delta_{i,k}\left(A\right)_{k,j}\\ & =\left(A\right)_{i,j} \end{align*} となるので
\[ AI_{n}=A \] となる。
同様に、任意の\(\left(i,j\right)\)成分について、
\begin{align*} \left(AI_{n}\right)_{i,j} & =\sum_{k=1}^{n}\left(A\right)_{i,k}\delta_{k,j}\\ & =\left(A\right)_{i,j} \end{align*} となるので
\[ I_{n}A=A \] となる。
従って、\(I_{n}A=AI_{n}=A\)となるので題意は成り立つ。
(4)
\(A\)を\(m\times n\)行列とする。任意の\(\left(i,j\right)\)成分について、
\begin{align*} \left(A+O_{m,n}\right)_{i,j} & =\left(A\right)_{i,j}+\left(O_{m,n}\right)_{i,j}\\ & =\left(A\right)_{i,j} \end{align*} \begin{align*} \left(O_{m,n}+A\right)_{i,j} & =\left(O_{m,n}\right)_{i,j}+\left(A\right)_{i,j}\\ & =\left(A\right)_{i,j} \end{align*} となる。
従って、\(A+O_{m,n}=O_{m,n}+A=A\)となる。
-
\(A\)を\(m\times n\)行列とする。任意の\(\left(i,j\right)\)成分について、
\begin{align*} \left(O_{l,m}A\right)_{i,j} & =\sum_{k=1}^{m}\left(O_{l.m}\right)_{i,k}\left(A\right)_{k,j}\\ & =\sum_{k=1}^{m}0\left(A\right)_{k,j}\\ & =0\\ & =\left(O_{l,n}\right)_{i,j} \end{align*} となる。
従って\(O_{l,m}A=O_{l,n}\)となる。
同様に、任意の\(\left(i,j\right)\)成分について、
\begin{align*} \left(AO_{n,l}\right)_{i,j} & =\sum_{k=1}^{n}\left(A\right)_{i,k}\left(O_{n,l}\right)_{k,j}\\ & =\sum_{k=1}^{n}\left(A\right)_{i,k}0\\ & =0\\ & =\left(O_{m,l}\right)_{i,j} \end{align*} となる。
従って\(AO_{n,l}=O_{m,l}\)となる。
-
\(A\)を\(n\)次正方行列とする。任意の\(\left(i,j\right)\)成分について、
\begin{align*} \left(O_{n}A\right)_{i,j} & =\sum_{k=1}^{n}\left(O_{n}\right)_{i,k}\left(A\right)_{k,j}\\ & =\sum_{k=1}^{n}0\left(A\right)_{k,j}\\ & =0\\ & =\left(O_{n}\right)_{i,j} \end{align*} \begin{align*} \left(AO_{n}\right)_{i,j} & =\sum_{k=1}^{n}\left(A\right)_{i,k}\left(O_{n}\right)_{k,j}\\ & =\sum_{k=1}^{n}\left(A\right)_{k,j}0\\ & =0\\ & =\left(O_{n}\right)_{i,j} \end{align*} となる。
従って、\(O_{n}A=AO_{n}=O_{n}\)となる。
(5)
行列は\(AB=O\)であっても\(A=O\lor B=O\)とは限らないことの証明反例で示す。
\[ A=\left(\begin{array}{cc} 1 & 0\\ 0 & 0 \end{array}\right) \] \[ B=\left(\begin{array}{cc} 0 & 0\\ 0 & 1 \end{array}\right) \] とすると、
\begin{align*} AB & =\left(\begin{array}{cc} 1 & 0\\ 0 & 0 \end{array}\right)\left(\begin{array}{cc} 0 & 0\\ 0 & 1 \end{array}\right)\\ & =\left(\begin{array}{cc} 0 & 0\\ 0 & 0 \end{array}\right)\\ & =O \end{align*} となるが、\(A\ne O\land B\ne O\)である。
従って、\(AB=O\)であっても\(A=O\lor B=O\)とは限らない。
-
\(AB=O\land A\ne O\land B\ne O\land A=B\)のとき、\(A^{2}=O\)となるのでべき零行列となる。例えば、
\[ A=\left(\begin{array}{cc} 0 & 1\\ 0 & 0 \end{array}\right) \] とすると\(A\ne O\)であるが\(A^{2}=O\)となる。
(6)
\(\Rightarrow\)
対偶で示す。すなわち、\(A\)がスカラー行列でないならば、ある\(n\)次正方行列が存在し可換でないことを示す。
\(A\)がスカラー行列でない、かつ、任意の\(n\)次正方行列と可換であると仮定する。
このとき、行列\(B_{p,q}\)を\(\left(p,q\right)\)成分が1でその他は0であるとする。
そうすると、
\begin{align*} \left(AB_{p,q}\right)_{i,j} & =\sum_{k=1}^{n}\left(A\right)_{i,k}\left(B_{p,q}\right)_{k,j}\\ & =\sum_{k=1}^{n}\left(A\right)_{i,k}\delta_{p,k}\delta_{q,j}\\ & =\left(A\right)_{i,p}\delta_{q,j} \end{align*} \begin{align*} \left(B_{p,q}A\right)_{i,j} & =\sum_{k=1}^{n}\left(B_{p,q}\right)_{i,k}\left(A\right)_{k,j}\\ & =\sum_{k=1}^{n}\delta_{p,i}\delta_{q,k}\left(A\right)_{k,j}\\ & =\delta_{p,i}\left(A\right)_{q,j} \end{align*} となるので、\(A,B_{p,q}\)が可換であるためには
\[ \left(A\right)_{i,p}\delta_{q,j}=\delta_{p,i}\left(A\right)_{q,j} \] となり、任意の\(p,q\)に対し成り立つので、\(i\ne p,j=q\)ととると、\(\left(A\right)_{i,p}=0\)となり、\(i=p,j=q\)ととると、\(\left(A\right)_{i,i}=\left(A\right)_{j,j}\)となる。
これより、\(A\)は非対角成分は0となり対角成分は全て同じ値になるので、\(\lambda\)をスカラーとすると\(A=\lambda I\)となりスカラー行列となり、\(A\)はスカラー行列でないという仮定に矛盾。
従って、背理法より、\(A\)がスカラー行列でないならば、ある\(n\)次正方行列が存在し可換でないことが示され対偶が示されたので、\(\Rightarrow\)が成り立つ。
\(\Leftarrow\)
\(A\)がスカラー行列であるならば\(A=\lambda I\)と表されるので、任意の\(n\)次正方行列\(B\)に対し、\begin{align*} AB & =\lambda IB\\ & =\lambda B\\ & =B\lambda\\ & =BI\lambda\\ & =B\lambda I\\ & =BA \end{align*} となるので可換である。
従って\(\Leftarrow\)が成り立つ。
\(\Leftrightarrow\)
これらより、\(\Rightarrow\)と\(\Leftarrow\)が成り立つので\(\Leftrightarrow\)が成り立つ。(7)
任意の\(\boldsymbol{x}\)に対し、\(\left(DE\right)\boldsymbol{x}=C\left(E\boldsymbol{x}\right)\)が成り立つので、\begin{align*} \left(\left(AB\right)C\right)\boldsymbol{x} & =\left(AB\right)\left(C\boldsymbol{x}\right)\\ & =A\left(B\left(C\boldsymbol{x}\right)\right)\\ & =A\left(\left(BC\right)\boldsymbol{x}\right)\\ & =\left(A\left(BC\right)\right)\boldsymbol{x} \end{align*} となり、\(\boldsymbol{x}\)について恒等的に成り立つには
\[ \left(AB\right)C=\left(A\left(BC\right)\right) \] となる。
従って結合律が成り立つ。
(8)
任意の\(\boldsymbol{x}\)に対し、\(\left(DE\right)\boldsymbol{x}=C\left(E\boldsymbol{x}\right)\)が成り立つので、\begin{align*} \left(A\left(B+C\right)\right)\boldsymbol{x} & =A\left(\left(B+C\right)\boldsymbol{x}\right)\\ & =A\left(B\boldsymbol{x}+C\boldsymbol{x}\right)\\ & =A\left(B\boldsymbol{x}\right)+A\left(C\boldsymbol{x}\right)\\ & =\left(AB\right)\boldsymbol{x}+\left(AC\right)\boldsymbol{x}\\ & =\left(AB+AC\right)\boldsymbol{x} \end{align*} となり、\(\boldsymbol{x}\)について恒等的に成り立つには、\(A\left(B+C\right)=AB+AC\)となり左分配律を満たす。
右分配律についても同様である。
従って題意は成り立つ。
ページ情報
| タイトル | 行列の性質 |
| URL | https://www.nomuramath.com/t4x0lwcb/ |
| SNSボタン |
トレースの性質
\[
\tr\left(AB\right)=\tr\left(BA\right)
\]
逆行列の性質
\[
\left(AB\right)^{-1}=B^{-1}A^{-1}
\]
正則行列の性質
\[
\det\left(A\right)\ne0\Leftrightarrow\ker\left(A\right)=\boldsymbol{0}
\]
エルミート転置の性質
\[
\left(AB\right)^{*}=B^{*}A^{*}
\]