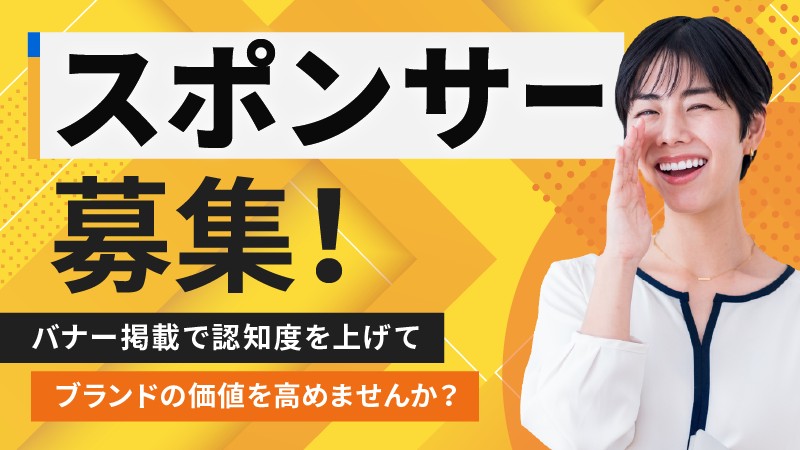方べきの定理
方冪の定理
このとき点\(P\)を通る直線が円Cに交わる交点を\(A_{1},A_{2}\)とすると、
\[ \left|PA_{1}\right|\left|PA_{2}\right|=\left|OP\right|^{2}-r^{2} \] となる。

\[ \left|PA_{1}\right|\left|PA_{2}\right|=\left|PB_{1}\right|\left|PB_{2}\right| \] が成り立つ。
これを方冪(ほうべき)の定理という。

また、線分\(A_{1}A_{2}\)の延長部分に点\(P\)があり、\(\left|PA_{1}\right|\left|PA_{2}\right|=\left|PB_{1}\right|^{2}\)となるとき、3点\(A_{1},A_{2},B_{1}\)はある円の円周上にあり、直線\(PB_{1}\)はその円に接する。

(1)
中心\(O\)、半径\(r\)の円\(C\)と\(C\)上にない点\(P\)をとる。このとき点\(P\)を通る直線が円Cに交わる交点を\(A_{1},A_{2}\)とすると、
\[ \left|PA_{1}\right|\left|PA_{2}\right|=\left|OP\right|^{2}-r^{2} \] となる。
(2)方冪の定理
点\(P\)を通る2直線を円\(C\)と交わるように引いて円\(C\)との交点を\(A_{1},A_{2}\)と\(B_{1},B_{2}\)とすると、\[ \left|PA_{1}\right|\left|PA_{2}\right|=\left|PB_{1}\right|\left|PB_{2}\right| \] が成り立つ。
これを方冪(ほうべき)の定理という。
(3)方べきの定理の逆
線分\(A_{1}A_{2},B_{1}B_{2}\)または線分\(A_{1}A_{2},B_{1}B_{2}\)の延長部分が1点\(P\)のみで交わり、\(\left|PA_{1}\right|\left|PA_{2}\right|=\left|PB_{1}\right|\left|PB_{2}\right|\)となるならば、4点\(A_{1},A_{2},B_{1},B_{2}\)はある円の円周上にある。また、線分\(A_{1}A_{2}\)の延長部分に点\(P\)があり、\(\left|PA_{1}\right|\left|PA_{2}\right|=\left|PB_{1}\right|^{2}\)となるとき、3点\(A_{1},A_{2},B_{1}\)はある円の円周上にあり、直線\(PB_{1}\)はその円に接する。
(1)
\(\boldsymbol{d}\)を任意の方向の単位ベクトルとする。点\(P\)を通る直線上の点と\(O\)からの距離が\(r\)になるためには、
\begin{align*} r^{2} & =\left(\overrightarrow{OP}+x\boldsymbol{d}\right)^{2}\\ & =x^{2}+2x\boldsymbol{d}\cdot\overrightarrow{OP}+\left|OP\right|^{2} \end{align*} となり、解と係数の関係より、\(x\)の2解\(x_{1},x_{2}\)の積は\(x_{1}x_{2}=\left|OP\right|^{2}-r^{2}\)となる。
\(\overrightarrow{PA_{1}}=x_{1}\boldsymbol{d},\overrightarrow{PA_{2}}=x_{2}\boldsymbol{d}\)に選ぶと\(\left|PA_{1}\right|\left|PA_{2}\right|=\left|x_{1}\boldsymbol{d}\right|\left|x_{2}\boldsymbol{d}\right|=x_{1}x_{2}=\left|OP\right|^{2}-r^{2}\)となるので題意は成り立つ。
(2)
(1)より、\begin{align*} \left|PA_{1}\right|\left|PA_{2}\right| & =\left|OP\right|^{2}-r^{2}\\ & =\left|PB_{1}\right|\left|PB_{2}\right| \end{align*} となるので与式は成り立つ。
(2)-2
点\(P\)が円の中にある場合
対頂角より\(\angle B_{1}PA_{1}=\angle B_{2}PA_{2}\)となる。また、弧\(\widehat{B_{1}A_{2}}\)の円周角より、\(\angle A_{2}A_{1}B_{1}=\angle A_{2}B_{2}B_{1}\)となる。
従って2角相当より、\(\triangle PA_{1}B_{1}\sim\triangle PB_{2}A_{2}\)となる。
これより、
\[ \frac{\left|PA_{1}\right|}{\left|PB_{1}\right|}=\frac{\left|PB_{2}\right|}{\left|PA_{2}\right|} \] となるので、
\[ \left|PA_{1}\right|\left|PA_{2}\right|=\left|PB_{1}\right|\left|PB_{2}\right| \] となる。
点\(P\)が円の中にあり\(B_{1}\ne B_{2}\)の場合
4角形\(A_{2}A_{1}B_{1}B_{2}\)は円に内接しているので、内角はその対角の外角に等しく、\(\angle B_{2}A_{2}A_{1}=\angle PB_{1}A_{1}\)となる。また、\(\angle A_{1}PB_{1}=\angle A_{2}PB_{2}\)であるので2角相当より、\(\triangle PA_{1}B_{1}\sim\triangle PB_{2}A_{2}\)となる。
これより、
\[ \frac{\left|PA_{1}\right|}{\left|PB_{1}\right|}=\frac{\left|PB_{2}\right|}{\left|PA_{2}\right|} \] となるので、
\[ \left|PA_{1}\right|\left|PA_{2}\right|=\left|PB_{1}\right|\left|PB_{2}\right| \] となる。
点\(P\)が円の中にあり\(B_{1}=B_{2}\)の場合
3角形\(A_{2}A_{1}B_{1}\)は円に内接していて、直線\(PB_{1}\)は円に接しているので接弦定理より、\(\angle B_{1}A_{2}A_{1}=\angle PB_{1}A_{1}\)となる。また、\(\angle A_{2}PB_{1}=\angle A_{1}PB_{1}\)であるので2角相当より、\(\triangle PA_{1}B_{1}\sim\triangle PB_{1}A_{2}\)となる。
これより、
\[ \frac{\left|PA_{1}\right|}{\left|PB_{1}\right|}=\frac{\left|PB_{1}\right|}{\left|PA_{2}\right|} \] となるので、
\[ \left|PA_{1}\right|\left|PA_{2}\right|=\left|PB_{1}\right|^{2} \] となる。
点\(P\)が円の中にあり\(A_{1}=A_{2}\)かつ\(B_{1}=B_{2}\)の場合
\(\left|PA_{1}\right|=\left|PB_{2}\right|\)なので明らかに成り立つ。-
これらより題意は成り立つ。(3)
線分\(A_{1}A_{2},B_{1}B_{2}\)が1点\(P\)のみで交わるとき
条件より、\(\left|PA_{1}\right|\left|PA_{2}\right|=\left|PB_{1}\right|\left|PB_{2}\right|\)なので、\[ \frac{\left|PA_{1}\right|}{\left|PB_{1}\right|}=\frac{\left|PB_{2}\right|}{\left|PA_{2}\right|} \] となる。
また、対頂角より、\(\angle B_{1}PA_{1}=\angle B_{2}PA_{2}\)となる。
従って2辺比夾角相等より、3角形\(PA_{1}B_{1}\)と3角形\(PB_{2}A_{2}\)は相似\(\triangle PA_{1}B_{1}\sim\triangle PB_{2}A_{2}\)となる。
これより、\(\angle A_{2}A_{1}B_{1}=\angle A_{2}B_{2}B_{1}\)となるので円周角の定理の逆より4点\(A_{1},A_{2},B_{1},B_{2}\)はある円の円周上にある。
線分\(A_{1}A_{2},B_{1}B_{2}\)の延長部分が1点\(P\)のみで交わるとき
条件より、\(\left|PA_{1}\right|\left|PA_{2}\right|=\left|PB_{1}\right|\left|PB_{2}\right|\)なので、\[ \frac{\left|PA_{1}\right|}{\left|PB_{1}\right|}=\frac{\left|PB_{2}\right|}{\left|PA_{2}\right|} \] となる。
また、\(\angle B_{1}PA_{1}=\angle B_{2}PA_{2}\)である。
従って2辺比夾角相等より、3角形\(PB_{1}A_{1}\)と3角形\(PA_{2}B_{2}\)は相似\(\triangle PB_{1}A_{1}\sim\triangle PA_{2}B_{2}\)となる。
これより、\(\angle B_{2}A_{2}A_{1}=\angle PB_{1}A_{1}\)となり、4角形\(A_{2}A_{1}B_{1}B_{2}\)の内角とその対角の外角が等しいので円に内接する4角形の対角の和の逆より4点\(A_{1},A_{2},B_{1},B_{2}\)はある円の円周上にある。
線分\(A_{1}A_{2}\)の延長部分に点\(P\) があり、\(\left|PA_{1}\right|\left|PA_{2}\right|=\left|PB_{1}\right|^{2}\)となるとき
条件より、\(\left|PA_{1}\right|\left|PA_{2}\right|=\left|PB_{1}\right|^{2}\)なので、\[ \frac{\left|PA_{1}\right|}{\left|PB_{1}\right|}=\frac{\left|PB_{1}\right|}{\left|PA_{2}\right|} \] となる。
また、\(\angle A_{1}PB_{1}=\angle A_{2}PB_{1}\)となる。
従って2辺比夾角相等より、3角形\(A_{1}PB_{1}\)と3角形\(B_{1}PA_{2}\)は相似\(\triangle A_{1}PB_{1}\sim\triangle B_{1}PA_{2}\)となる。
これより、\(\angle B_{1}A_{2}A_{1}=\angle A_{1}B_{1}P\)となるので接弦定理の逆より、3点\(A_{1},A_{2},B_{1}\)はある円の円周上にあり、直線\(PB_{1}\)はその円に接する。
-
これらより題意は成り立つ。ページ情報
| タイトル | 方べきの定理 |
| URL | https://www.nomuramath.com/o54anj4t/ |
| SNSボタン |
正n角形の面積
\[
S=\frac{na^{2}}{4\tan\frac{\pi}{n}}
\]
点と超平面・直線の距離
\[
d=\frac{\left|\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{OP}+a\right|}{\left|\boldsymbol{n}\right|}
\]
外接円を持つ4角形の角度と対角線の長さ
\[
p=\sqrt{\frac{cd\left(a^{2}+b^{2}\right)+ab\left(c^{2}+d^{2}\right)}{ab+cd}}
\]
接弦定理
\[
\angle BAP=\angle BCA
\]